2 マザコンのバルザック?

出典:Pixabay
母親のことを大層冷たく書くバルザックは、実は自分でも意識していないマザコンだったのではないだろうか。この部分に光を当てた評論は見当たらず、バルザックが母親に与えた評価(酷評)がそのまま罷り通っている。母親宛の書簡から、バルザックが母親をすっかり召使いにしてしまっていたことがわかる。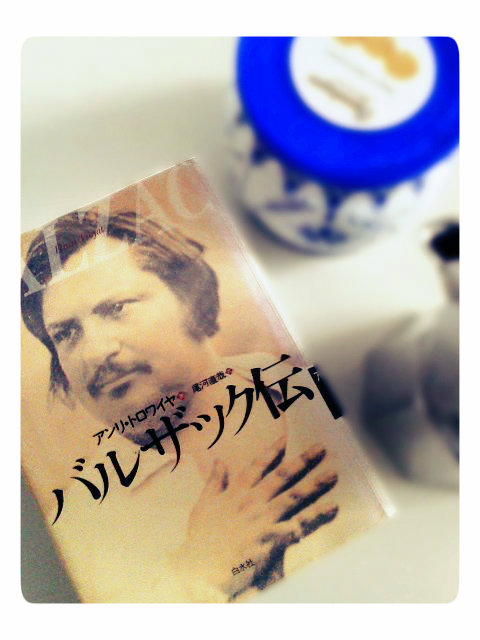
この部分に光を当てた評論は見当たらず、バルザックが母親に与えた評価(酷評)がそのまま罷り通っている。母親宛の書簡から、バルザックが母親をすっかり召使いにしてしまっていたことがわかる。
母親が何もしてくれない、冷たいとバルザックが愚痴を零すのが不可解に思われるほど、母親は彼のために尽くしている。あるいは幾分かは息子に貸した大金を返して貰いたかったからかもしれないが、それにしても彼の大変な局面に、母親が顔を出しすぎる。
彼は書簡で母親に、性欲の処理がうまくいかないことをさえ、訴えているのだ。こうなるともはや、マザコンの域を超えて、バルザックは母親を人間扱いしていなかったとすら想像されるほどだ。わたしにも息子がいるが、そんなことを訴えかけられたときの母親の気持ちというものは、どんなものなのだろう。大変なこと、つらいことは全て母親に投げかけて苦労を共にさせ、余裕のある小綺麗な自分を彼は、永遠の愛人と謳うベルニー夫人や結婚相手となったハンスカ夫人に与えたのではなかったか?
また、母親の知的理解力は、相当なものであったと思われる。母親は校正を手伝い、作品に鋭い感想を述べたりする。そしてバルザックは、母親が集めた神秘主義関係の蔵書をかなり活用したらしい。これは余談であるが、バルザックはバラ十字会員だったのではないかと思う。
なぜなら、わたしが神智学協会を知る前にバラ十字会にコンタクトをとり、資料を取り寄せたことがあって、その入会案内にバルザックがバラ十字会員であったことを記載してあったからだ。父親はフリーメーソンだったと伝記作家たちは述べているが、母親はバラ十字会員だった可能性がある。当時西洋で神秘主義を知ろうとするなら、この二つのどちらかに入会せざるをえなかっただろうと思う。
東西の神秘主義を総合し、近代神智学を創始したブラヴァツキーは、彼女の代表的な著書である『シークレット・ドクトリン』の中で、バルザックのことを「フランス文学界最高のオカルティスト(本人はそのことに気づかなかったが)」といい、創造に関わる数の秘密について触れたバルザックの文章を紹介している。
実際、『ルイ・ランベール』のような難解極まる、それでいて統一のとれた理論を展開した近代神秘主義の申し子ともいえるような作品は、人が自分一人で考えついて書けるような代物ではない。
当時の神秘主義者たちを邸に招いたり、書物を集めたりした謎めいたところのある母親に比べ、バルザックの賛美の対象であったベルニー夫人やハンスカ夫人の方は、書簡から察せられるに、如何にも常識的なキリスト教徒という感じだ。尤も、神秘主義はバルザックが生きた時代には今とは違い、古くて新しい、がキリスト教からすれば当然危険な、心躍らせる流行の思想でもあったようだ。
それにしても、フランス語で書かれた文献が読めないのは、何とも不自由だ。せめてもの慰めに、フランスのバルザック『人間喜劇』のホームページから、神秘主義思想が芳醇に香る『ル・リス・ダン・ラ・バレ(谷間の百合)』の初めの部分を引き出して、原文の香りを堪能した。
こうして用紙に印字したバルザックの作品を手にしてみると、邦訳されて製本されたものとは一味違った、生々しさを覚える。長大な『谷間の百合』といえど、額に汗して、一頁一頁書かれたのだということが感覚的に伝わってくるのだ。
バルザックの文章は悪文だといわれるが、なるほどと思う。説明に説明を次ぐ書き方で、だらだら、くどくどと続くのだ。文章の美観より、思想の美観に気を配り、読者に伝えたいことを率直に愚直に書いていくタイプの作家なのだろう。だが、決して無骨ではなく、文章はポタージュのようにこくがある(ように感じられる)。
外国語がろくにできない段階にあってさえ、原文に接してみることは大事だと改めて思った。ブラヴァツキーの原文に接したときのように。だいたい翻訳された書物と原書とでは、本から出ているオーラの色合いが違う。
日本の作家のものでは、泉鏡花、織田作之助の文章のようなものは、翻訳すれば、その香気が失せてしまうだろう。世阿弥の『風姿花伝』『花鏡』のような妙なる調べを持つ文章はいうに及ばない。
マダムNの覚書、2006年4月15日 (土) 11:45
〔追記〕
伊藤幸次著『バルザックとその時代』(渡辺出版、平成16年)によると、バルザックの父親の家系は バルサという姓で、南フランスの地中海岸、ラングドック人であったということだ。母親はパリの裕福な商人の娘。
バルザックが「二十歳になる迄、自分をラングドック人として意識し、かつそれを表明していた」にも拘らず、それ以降、父方の家系を意図的に拭い去ろうとした形跡があるそうだ。その理由として、次のような事実が挙げられている。
父親の弟ルイ・バルサが「定額小作人の娘セシール=スイエを殺害したかどにより逮捕されていた。娘がルイの子供を宿したため、彼が暴力によって解決を図ったと見られたのである。1819年6月アルビの重罪裁判所にて有罪判決を受け、同年8月16日、恐らく無実であったらしいルイは、アルビにてギロチンにかけられる」。この事件はバルザックの作品『村の司祭』を連想させる。
わたしにとって、バルザックがラングドック人であったという事実は、興味深い。なぜなら、ラングドックというと、異端カタリ派を連想しないわけにはいかないからだ。
ラングドックは異端カタリ派の牙城となった。異端カタリ派が活発な活動を行っていた12世紀頃のラングドックは、原田武著『異端カタリ派と転生』(人文書院、1991年)によると、経済活動の活発な、文化的な先進地域だった。異端カタリ派には本来、知的で都会的な傾向があったということだ。至純の愛を謳う吟遊詩人たち――トゥルバドゥールの華やかな活躍もあった。
バルザックが二十歳以降ラングドック人としての自分を消そうとしたにも拘らず、その思想にはラングドック人の雰囲気が感じとれる気がする。
2008年4月12日