86 シモーヌ・ヴェイユと母セルマとガリマール書店の〈希望〉叢書

アッシジ(イタリア、ウンブリア州ベルージャ県)
出典:Pixabay
22 グレイ著『ペンギン評伝双書 シモーヌ・ヴェイユ 』を読了後に
23 ミクロス・ヴェトー(今村純子訳)『シモーヌ・ヴェイユの哲学―その形而上学的転回』から透けて見えるキリスト教ブランド
24 ルネ・ゲノンからシモーヌ・ヴェイユがどんな影響を受けたかを調べる必要あり
86 シモーヌ・ヴェイユと母セルマとガリマール書店の〈希望〉叢書

シモーヌ・ヴェイユ(不詳)
出典:Wikimedia Commons
図書館から借りた『別冊水声通信 シモーヌ・ヴェイユ』(編集発行人・鈴木宏、水声社、2017)に、アルベール・カミュがシモーヌ・ヴェイユに関して書いた短い文章が収録されていた。
アルベール・カミュ(Albert Camus,1913 - 1960)はフランス領アルジェリアの出身で、純文学小説『異邦人』、哲学的エッセー『シーシュポスの神話』で有名になったフランスの作家である。カミュは不条理という言葉を『シーシュポスの神話』で鮮烈に用い、その後、この言葉は実存主義の用語となった。不条理とは、人間存在の根源的曖昧さ、無意味さ、非論理性に由来する絶望的状況を意味する言葉とされる。
わたしの大学のころ――40年ほども昔の話になる――には、第二次大戦後にフランスからサルトルなどによって広まった実存主義はまだ流行っていた。
否、今でも哲学的主流はこのあたりに停滞していて、現代哲学は唯物論に依拠して局部的、細部的分析に終始しているのではないだろうか。
カミュは自分では実存主義者ではないとしているが、その思想傾向からすれば、実存主義者に分類されてよいと思われる。
カミュに発見されたといってよい女性哲学者シモーヌ・ヴェイユ(Simone Weil, 1909 - 1943)はパリでユダヤ系の両親から生まれ、晩年、キリスト教的神秘主義思想を独自に深めていったが、しばしば実存主義哲学者に分類される。だが、そのシモーヌも、ジャン・ヴァールへの手紙で次のように書いて、実存主義に警戒心を抱いていたようである。シモーヌ・ペトルマン(田辺保訳)『詳伝 シモーヌ・ヴェイユ Ⅱ』(勁草書房、1978)より、引用する。
わたしは、《実存主義》的な思想の流れは、自分の知るかぎりにおいて、どうやらよくないものの側に属するように思えますことを、あなたに隠しておくことができません。それは、その名が何であれ、ノアが受け入れ、伝えてきた啓示とは異種の思想の側に、すなわち、力の側に属するように思われます。*1
実存主義はマルクス主義の影響を受けた思想で、唯物論的であり、マルクス主義の流行とも相俟って一世を風靡した。しかし、一端、唯物論的袋小路へ入り込んでしまうと、自家中毒を起こし、下手をすれば阿片中毒者のような廃人になってしまう危険性さえある。
村上春樹のムーディ、曖昧模糊とした小説はこうした不条理哲学の子供――ただし、カミュの作品が持つ聡明さ、誠実さを欠いた子供といえる。戦後、日本はGHQによる洗脳工作(WGIP)や公職追放*2などもあって、唯物主義、物質主義が優勢となったのだった。
わたしが「カミュに発見されたといってよい女性哲学者シモーヌ・ヴェイユ」と先に述べたのは、シモーヌ・ヴェイユ(田辺保訳)『超自然的認識』(勁草書房、1976)の訳者あとがきで述べられている、次の文章を根拠としたものだった。
ガリマール社版のシモーヌ・ヴェイユの著作はほとんどすべて、本書と同じ「希望[エスポワール]」双書に収められているが、この双書はアルベール・カミュ(1913―60)によって創設された。第二次大戦下の英国において、34歳で死んだ、当時まったく無名だったといっていいシモーヌ・ヴェイユを、戦後のフランスの思想界に紹介した大きい功績は、当然第一にカミュに帰せられるべきであるが、本書の編集も(明記されてはいないが)、カミュであるとみなすことは充分に可能である。*3
現在60歳のわたしが、『超自然的認識』によってシモーヌ・ヴェイユの思想に触れたのは大学時代だった。この本には「プロローグ」というタイトルで、シモーヌ・ヴェイユの有名な美しい断章が紹介されていた。
『超自然的認識』の新装版がアマゾンに出ていたので、紹介しておく。
『超自然的認識』を読んだときから、シモーヌの作品の邦訳版を読み漁り、またシモーヌとカミュとの接点を求めて、あれこれ読んだ。カミュがシモーヌを発見した人物であることを雄弁に物語っているような文章には、出合えなかった。
邦訳されていないだけだと思っていたのだが、『別冊水声通信 シモーヌ・ヴェイユ』(編集発行人・鈴木宏、水声社、2017)に収録されたアルベール・カミュの文章、及び解説を読んで、シモーヌの母セルマの関与が浮かび上がってきた。
訳出されたカミュの文章は、竹内修一氏の解説によると、『NRF出版案内』1949年6月号に発表された「シモーヌ・ヴェイユ」と題された文章だという。
カミュがシモーヌの発見者であるにしては、その文章の内容からしてシモーヌを高く評価していることに間違いはないにせよ、短いというだけでなく、いささか精彩を欠くものであるようにわたしには思える。竹内氏は述べている。
1943年8月、ロンドン郊外のサナトリウムで死したとき一般の人々にはほとんど知られていなかったシモーヌ・ヴェイユが、戦後これほど有名になるためには、彼女が「生涯のあいだ頑なに拒否した「第一級の地位」を獲得するためには、みずからが監修していたガリマール書店の〈希望〉叢書から彼女の著作を次々に刊行したカミュの功績があったのである。*4
ところが、この叢書が1946年3月に創刊されたとき、カミュはヴェイユのことをほとんど知らなかったばかりか、シモーヌの遺作の出版は全く予定されていなかったというのだ。
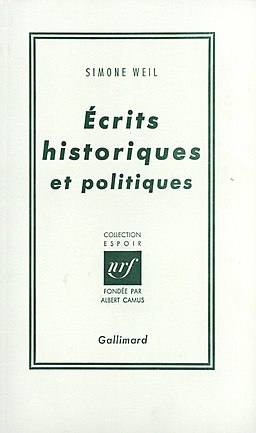
シモーヌ・ヴェイユの歴史的・政治的著作の初版のカバー
出典:Wikimedia Commons
カミュの文章「シモーヌ・ヴェイユ」は本来なら〈希望〉叢書の9冊目の書物『根をもつこと』のための序文として書かれたものだった。それがヴェイユの遺産相続者――シモーヌの父母なのか、兄アンドレなのかは不明――の依頼によるものか、あるいは何らかのトラブルによって、この文章は別個に発表された。『根をもつこと』は序文も注釈もなしに出版されたのだそうだ。
1960年にカミュが自動車事故で死んだとき、〈希望〉叢書24作品のうちの7つの作品がシモーヌ・ヴェイユの著作だった。カミュの死後も2つのシモーヌの作品が出版された。
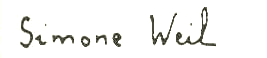
シモーヌ・ヴェイユの署名
出典:Wikimedia Commons
竹内氏の解説中、ギー・バッセによれば、〈希望〉叢書から出版されるシモーヌの著作に無署名の「刊行者のノート」が付されたとすれば、それはカミュではなく、母セルマが作成したものだという。
シモーヌ・ヴェイユの兄アンドレ・ヴェイユの娘で、シモーヌの姪に当たるシルヴィ・ヴェイユ(1942 - )は自著(稲葉延子訳)『アンドレとシモーヌ ヴェイユ家の物語』(春秋社、2011)の中で、シモーヌの死後、アンドレと両親との間にシモーヌの死や彼女の自筆原稿をめぐって亀裂が生じたと述べている。シモーヌの死後、ヴェイユ夫妻の残りの人生は娘の原稿を後世に残すための清書に費やされたそうだ。
シルヴィはその著書で、「父はこの分析が正しいのかどうかはわからないが、自分の母親がシモーヌの内に、母親がいなくてはならない状態をつくりあげ、それが原因でシモーヌは死んだと見做していた」*5と述べている。
また、エッセー 22「グレイ著『ペンギン評伝双書 シモーヌ・ヴェイユ 』を読了後に」で採り上げたフランシーヌ・デュ・プレシックス・グレイは、シモーヌの摂食障害――拒食症の傾向――に迫っている。
これはわたしの憶測にすぎないが、シモーヌ・ヴェイユの母セルマは、豊かな財力によってカミュが監修していたガリマール書店の〈希望〉叢書の9つの出版枠を買い取ったのではないだろうか。

シモーヌ・ヴェイユの墓
出典:Wikimedia Commons
我が身に自ら拘束帯をつけたかのような、ストイックすぎる生きかたをしたシモーヌ・ヴェイユ。高純度の思想を書き残したシモーヌと母セルマを思うとき、一卵性親子と呼ばれた美空ひばり(加藤和枝)と母・加藤喜美枝を連想してしまう。
セルマには、シモーヌをプロデュースしたステージママのような一面があったように思う。シモーヌは哲学者となり、兄のアンドレは高名な数学者となった。
『詳伝 シモーヌ・ヴェイユ Ⅰ・Ⅱ』『ペンギン評伝双書 シモーヌ・ヴェイユ』『アンドレとシモーヌ ヴェイユ家の物語』を読むと、セルマの並外れた母親ぶりに圧倒される。
わたしはエッセー 23「ミクロス・ヴェトー(今村純子訳)『シモーヌ・ヴェイユの哲学―その形而上学的転回』から透けて見えるキリスト教ブランド」で、次のように書いた。
シモーヌ・ヴェイユは、おそらく母親の偏愛――シモーヌ・ヴェイユが理想とする愛とはあまりにもかけ離れたものを含む現象――を感じ、その呪縛性を知りつつも、それをそっとしておき、恭順の意さえ示している。キリスト教に対する態度も同じだったように思える。
彼女はキリスト教というブランドを非難しつつも、それに屈し、媚びてさえいる。その恭順の姿勢ゆえに、シモーヌ・ヴェイユという優等生は西洋キリスト教社会では一種聖女扱いされてきたということがいえると思う。
シルヴィ(稲葉訳,2011,pp.157-159)によると、セルマは演劇的な人物だった。シモーヌの死後は聖女の母という役を演じて能力を開花させ、修道女のような態でシモーヌの賞賛者である限られた数人の聖職者たちと亡き娘の部屋に籠っていたという。
シルヴィ(稲葉訳,2011,pp.157-176)はまた、17歳のセルマが母親ジェルトルード宛の手紙に「使用人と類する人たち」に対する嫌悪感を綴ったこと、その同じ人物が第一次大戦後ほどなくヴァカンスで過ごした豪奢なホテルのサロンにあるピアノで「革命家インターナショナル」を笑いながら自慢げに演奏し、組合主義者の教師となったシモーヌが右翼メディアに「赤い聖処女」と採り上げられたときには、その赤い聖処女の母という役回りに愉悦していたという事実が信じられないと語る。

シモーヌ・ヴェイユと生徒(ル・ピュイ)
出典:Wikimedia Commons
完全主義者で所有欲が強く、演劇的で矛盾に満ち、絶え間なくシモーヌを見守った――ある意味で操ったとさえいえる――セルマは、どこか世俗キリスト教と重なる。
『詳伝 シモーヌ・ヴェイユ Ⅱ』の著者シモーヌ・ペトルマンは、ヴェイユの最も親密な友人の一人であったそうだが、「日本語版によせて」の最後に、次のように書いている。
シモーヌ・ヴェイユは宗教問題に深い関心を寄せていましたが、それはキリスト教の限界を越えるものだったことを、もう一度思い出しておきたいと思います。特に彼女は、禅仏教に強い興味を示していました。フランスにおいて、禅なんてほとんどまったく知られずにいた時代のことでした。*6
その禅とは、鈴木大拙の著書を通したものだったと考えてよい。シモーヌ・ヴェイユは、ペトルマン宛の手紙で次のように書いている。
英語で書かれた、禅仏教に関する、哲学者鈴木テイタロー[大拙、仏教哲学者]の著書をおすすめします。とてもおもしろいわよ。*7
エッセー 24 「ルネ・ゲノンからシモーヌ・ヴェイユがどんな影響を受けたかを調べる必要あり」で書いたように、鈴木大拙は神智学協会の会員だったから、シモーヌ・ヴェイユは大拙の著作を通して近代神智学思想に触れたといえるかもしれない。
しかし、その同じシモーヌ・ヴェイユがルネ・ゲノンという、極めて混乱した宗教観と貧弱な哲学しか持ち合わせないばかりか、近代神智学の母と謳われるブラヴァツキーの代表的著作すらろくに読んだ形跡がないにも拘わらず、神智学批判を行った――これは誹謗中傷というべきだろう――人物の著作の愛読者だったそうだから、わたしはあれほどまでに輝かしい知性の持主のシモーヌがなぜ……と、違和感を覚えずにはいられない。
それは、シルヴィが祖母セルマに感じたのと同じような、信じられない思いである。